♯貯金

「老後にお金がない」「みじめな生活だと感じる」このような悩みや不安を抱えてはいませんか。
生活費が高騰するなかで、受け取れる年金が変わらないことから日々の生活に苦しさを感じる高齢者も少なくないでしょう。
「物価上昇で日々の支払いで精一杯…貯金なんてできそうもない」
「子どもの教育費を貯めたいけど貯金に回す余裕がない」
貯金がないことに対する焦りは、将来に対する不安にもつながります。
今回は貯金がない家庭は多いのか、データを見ながら解説していきます。
また、貯金がない家庭の特徴や貯金の増やし方についてもご紹介します。
貯金は一朝一夕でできるものではありません。コツコツ積み重ねていくことでしか増えていかないものです。
しかし、仕組みさえつくれえば貯められるようになります。すぐできる方法ばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。
各年代の平均貯金額とは

金融広報中央委員会が公表した「家計の金融行動に関する世論調査(平成30年)」によると各年代の平均貯金額は以下のような結果になっています。
- 20歳代:283万円
- 30歳代:450万円
- 40歳代:673万円
- 50歳代:849万円
- 60歳代:1,290万円
- 70歳以上:1,555万円
- 全体平均:1,035万円
「20歳代で既に283万円も貯金しているの?」と驚いた人も多いと思います。
しかし、これはあくまでも平均です。平均は極端に貯金額が多い人がいる場合には、それらに引き寄せられるため、現状を正しく反映できていない場合があります。
年代別の平均貯金額だけでは現状が分かりにくいため、続いて年収別の平均貯金額も見ていきましょう。
年収別の平均貯金額とは
同調査の年収別の平均貯金額は以下のような結果になっています。
- 300万円未満:804万円
- 300~500万円未満:946万円
- 500~750万円未満:966万円
- 750~1,000万円未満:1,079万円
- 1,000~1,200万円未満:1,435万円
- 1,200万円以上:2,308万円
年収300万円未満には、退職した後に多少の収入がある人も含まれ、これまでの貯金も反映されています。
そのため、本当に年収300万円未満の人の貯金は、もっと少ないと考えられます。
しかし、300万円以上は、基本的には実際の収入が反映されていると考えられるため、各年代と各年収の平均貯金額を見ながら貯金の目標を立てるようにしましょう。
老後にお金がない・みじめな生活と感じる人の5つの特徴

老後にお金がないことから、みじめな生活を送っていると感じている人はどのような特徴があるのでしょうか。
ここでは、以下の5つを紹介します。
みじめな生活と感じる人の特徴
・収支のバランスが悪い
・借金やローンの返済がある
・浪費癖がある
・貯蓄がないのに見栄を張る
・投資やギャンブルに失敗する
老後にお金がなく、みじめな生活を未然に防ぎたい人にチェックしておいてほしい内容となっています。
収支のバランスが悪い
老後にお金がない人は、入ってくるお金に対して出ていくお金が多くなっている場合が多いです。
支出が大きいほど、お金が減っていく不安が大きくなるでしょう。
特に、入ってくるお金をすべて使ってしまうような生活を送っている人は要注意です。
年金生活となり、現役世代より収入が減っている状態で、支出が変わらなければ、お金が足りなくなるのは当然です。
また、年齢を重ねると医療費や介護費用などの費用がプラスとなる可能性が高まります。
通院にかかる交通費などの支出も増えがちなので、収入が下がってしまったタイミングで何にお金を使っているのか見直しをしてみるとよいでしょう。
借金やローンの返済がある
現役世代のときに作った借金や長期で組んだローンの返済がある場合は、毎月決まったお金が返済に充てられます。
返済額が大きいほど、貯蓄が底をつくタイミングも早まってしまうでしょう。
特に40~50代でローンを組んだ人は、老後にも返済が残る可能性があるので、リスクが高いといえます。
家計への大きな負担となるので、ローンを組むときは事前に返済計画をしっかりと確認することが大切です。
老後でも返済できる金額か、もしくは現役世代で返済ができないか確認しておきましょう。
浪費癖がある
毎月の収支を把握していなかったり、何にいくら使っているのかを気にしていなかったりする人は、お金がなくみじめに感じる可能性があります。
少額のものから高額なものまで、衝動的に買ってしまう人や買い物がやめられない人などは注意しましょう。
まずは収入や貯蓄を把握し、何にいくらお金を使っているのかを知ることが大切です。
買い物好きな人は、本当に必要なものなのかを考えてから購入しましょう。
すぐ買うのではなく、時間を置いてから本当に必要なものなのか検討して購入することをおすすめします。
貯蓄がないのに見栄を張る
貯蓄がない、もしくは少ないのに、見栄を張って高級品を身に着けたり、食事代を払おうとしたりする人は要注意です。
誰もが自分をよく見せたいものですが、本来必要のないものにお金をかけることでみじめな生活につながる可能性があります。
さらに、借入までしてしまうとあとから返済に追われ、後に引けない状況になってしまいます。
お金を使わない楽しみ方や趣味を見つけ、日々の生活を充実できるように見直していきましょう。
一瞬の見栄が、あとからみじめな生活を引き起こす可能性があることを知っておくことが重要です。
投資やギャンブルに失敗する
ハイリスクな投資(株やFX、仮想通貨など)で大きなお金を失う人や、ギャンブルに大金を使う人は、老後にお金がなくみじめな生活だと感じてしまう可能性があります。
気をつけるべきポイントは、退職金を受け取ったときです。
勧められるがままにリスクの高い資産運用の商品を購入したり契約したりしないように気をつけましょう。
不利益となる可能性があることをよく理解しないまま、話を進めるのは大変危険です。
正しい金融の基礎知識を身に付けて投資をおこなうか、リスクがある商品に高額のお金を使わないようにします。
ギャンブルも趣味で楽しめる範囲内でおこないましょう。
貯金がない家庭は多い?

貯金がない家庭は実際にどれくらいいるのでしょうか。具体的なデータを見ていきましょう。
年代別での貯金がない割合
まずは年代別での割合を見ていきましょう。金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和4年)」によると、金融資産を保有していない世帯は次のとおりです。
| 世帯主の年齢 | 金融資産を保有していない割合 |
| 20歳代 | 40.6% |
| 30歳代 | 26.7% |
| 40歳代 | 28.4% |
| 50歳代 | 28.4% |
| 60歳代 | 23.1% |
| 70歳代 | 21.8% |
20歳代では40.6%となっており、2人に1人に近い人数が貯金がないとしています。働き始めて年数が経っていないこともあり、若い年代ほど貯金がない割合が多いことがわかります。
しかし、40歳代・50歳代でも28.4%と、約3人に1人が貯金がないと回答しています。子どもも大きくなり、教育費がかかってくることから、貯金がしづらい状況であると予想できます。
世帯別での貯金がない割合
単身世帯と2人以上の世帯の貯金状況に違いはあるのでしょうか。まずは単身世帯の貯金がない割合を見ていきましょう。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年)」によると、34.5%と3人に1人以上が「貯金がない」としています。
一方、2人以上の世帯は23.1%となっており、単身世帯と比較すると低いものの、一定数いることがわかります。
なお、世帯主の年齢別に比較したものは、次のとおりです。
| 単身世帯 | 2人以上世帯 | |
| 20歳代 | 42.1% | 35.7% |
| 30歳代 | 32.4% | 23.9% |
| 40歳代 | 35.8% | 26.1% |
| 50歳代 | 39.6% | 24.4% |
| 60歳代 | 28.5% | 20.8% |
| 70歳代 | 28.3% | 18.7% |
どの年齢においても、単身世帯の方が貯金がない家庭は多くなっています。また、2人以上の世帯は、世帯主の年齢が上がるにつれて、貯金がない家庭が少なくなっていくのがわかります。
貯金がない家庭の理由・特徴

貯金がない家庭の割合を見てきました。20歳代においては約2人に1人が貯金がないと回答している一方で、貯金ができている人もいます。
この違いは何なのか、貯金がない家庭の理由や特徴をみていきましょう。
収支を把握できていない
貯金がない家庭の特徴として、収支を把握できていない点が挙げられます。収入に対して、どれくらいの支出があるのかがわからなければ、「実は赤字だった…」という状況になっているかもしれません。
また、最近は電子マネーやQRコード決済など、現金でやりとりをすることも少なくなり、お金を払っている感覚が薄くなっています。
家計簿をつけたり、クレジットカードの利用状況を確認したり、収支を把握することが大切です。
貯金の目標や目的がない
貯金の目標や目的がないと、貯金に対するモチベーションが維持しにくいため、なかなか貯められません。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和4年)」によると、金融資産保有額別の金融資産の保有目的は次のようになっています。
| 金融資産保有目的 | 金融資産保有額 | ||
| 100万円未満 | 500〜700万円未満 | 1,000〜1,500万円未満 | |
| 病気や不時の 災害への備え | 44.7% | 50.7% | 53.3% |
| 子どもの教育資金 | 22.2% | 30.6% | 23.6% |
| 子どもの結婚資金 | 4.8% | 5% | 5.1% |
| 住宅の取得または 増改築などの資金 | 7% | 12% | 10.4% |
| 老後の生活資金 | 42.9% | 65.3% | 75.2% |
| 耐久消費財の 購入資金 | 8.3% | 10.5% | 15.2% |
| 旅行、レジャーの 資金 | 16.6% | 16% | 19.8% |
| 納税資金 | 4.4% | 2.3% | 1.2% |
| 遺産として 子孫に残す | 2.4% | 4.1% | 8.7% |
| 特に目的はないが、金融資産を保有していれば安心 | 19.6% | 16.3% | 15.9% |
上記は3つまでの複数回答となっており、教育費や住宅の購入費、老後費用など、資産がある世帯ほど先々を見て、目的意識を持って貯金をしていることがわかります。
贅沢品にお金を使う
貯金ができない家庭の特徴として、贅沢品にお金を使うことが挙げられます。例えば、ボーナスが入ったときに旅行に行ったり、家電製品を買ったり、贅沢品に使っていると貯金ができません。
貯金ができている家庭は、ボーナスをないものとして考え、普段の生活費から旅行費や家電の購入費を貯めるようにしています。
そして、ボーナスは貯金に回したり、返済に充てたり、資産を増やす、もしくは減らすことに使っています。
とはいえ、全く使わないのも生活に対する満足度が低くなってしまうでしょう。予算を決めて使う、貯金に回したあとで贅沢するなど、計画性を持つことが大切です。
貯金がない家庭が抱えるリスク
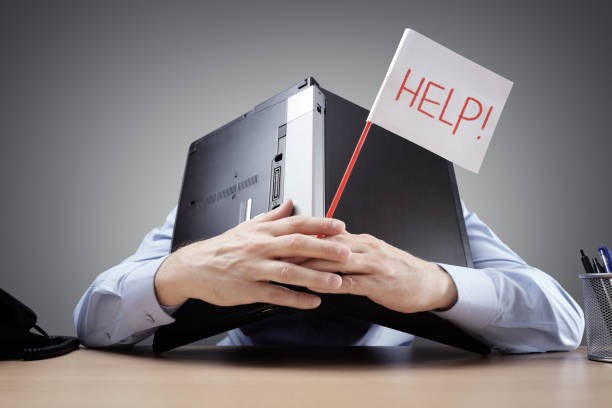
「貯金がなくても今まで何とかなっていた」と考える方もいるかもしれません。しかし、貯金がないのはリスクがあります。ここでは、貯金がないとどういったリスクがあるのか詳しく見ていきます。
急な出費に対応できない
貯金がないリスクの1つ目は、急な出費に対応できないことです。例えば、病気やケガをして働けなくなったり、車が壊れたりなど、こういった事態は予測できません。
もし起こったときに、貯金がなければ対応できず、生活が苦しくなってしまう可能性があります。
そのため、生活防衛資金を用意することが大切です。一般的に生活費の半年分が目安とされています。
将来への備えができない
貯金がない家庭は、将来への備えができないというリスクがあります。子どもの教育費や老後の生活費など、まとまった金額が必要になったときに対応できません。
特にこれらは、必要になる時期がわかっています。もし備えができていなければ、奨学金を借りたり、老後も働かざるをえなかったりと、苦労することが増えるでしょう。
貯金があれば、奨学金を借りたとしても少額で済み、老後の収入も少なく済みます。
理想とするライフイベントを送れない
貯金がない家庭は、理想とするライフイベントを送れない可能性があります。例えば、老後には世界一周旅行をしたいと思っていても、貯金がなければ叶えられません。
また、老後だけでなく、子どもの進学、結婚式、住宅の購入など、理想を叶えるためには、ある程度の貯金は必要となります。
もし貯金がなければ、たとえ叶えられたとしても、質を下げなければいけなくなるなど、満足度は下がるでしょう。
理想とするライフイベントを送るためには、コツコツ貯金することが大切です。
老後の生活でお金がない・みじめな生活を送らないための方法7選

老後にお金がないときや、みじめな生活だと感じないために事前にできる方法は以下の8つです。
具体的にそれぞれ確認していきましょう。
事前にできる方法
・収支の状況を把握する
・固定費の見直しをする
・可能な限り働く
・健康寿命を延ばすために規則正しい生活を送る
・自宅を売却する
・借入返済に悩んでいる場合は専門家に相談する
・他人と比べない
・現役世代は資産運用をおこない資産を増やす
収支の状況を把握する
収入と支出を把握し、お金の流れを確認します。
簡単な流れは以下のとおりです。
- 1.すべての収入額を知り、毎月いくら振り込まれているかをチェック
- 2.簡易的なものでもよいので家計簿をつけて、支出を確認
- 3.支出の割合が多い項目を重点的に節約するように心がける
節約する場合に注意すべき点は、健康に影響の出る光熱費(夏場にエアコンを使わないなど)や食費は一定額確保するようにすること。
健康を害してしまうと病院へ行くことが増え、より支出が増加します。
健康を意識しながら生活費の節約をしましょう。
固定費の見直しをする
効果的な節約につながるケースが多いため、まずは固定費から見直しましょう。
以下のような項目のチェックがおすすめです。
| 項目 | 内容 |
| 電気・ガス・水道 | ・契約会社や適切なプランへの見直し ・比較サイトを使ってチェック |
| 家賃 | ・家賃の安いところへ引っ越す ・引越代でまとまったお金が必要になるが、 長期的に見ると月々数千円~数万円の節約となる |
| スマホ | ・格安SIM(格安スマホ)への見直し ・適切なプランになっているか確認 |
| 保険 | ・加入中の保険の見直しで、月々の保険料負担を減らす ・損害保険(自動車・火災保険)は、補償内容を確認し、 適切な内容かチェック |
保険の見直しでお困りの方は「みんなの生命保険アドバイザー」での相談がおすすめです。
ファイナンシャルプランナーが、直接訪問もしくはオンラインで相談を受け付けます。
何度相談しても無料なのでおすすめです。
可能な限り働く
年金受給年齢になった場合でも、健康なうちはできるだけ長く働き収入源を確保しましょう。
別の収入が確保できると年金受給を繰り下げられるため、月々の受取額を増やすことが可能です。
政府は70歳までの定年引き上げや再雇用制度・勤務延長制度を企業に導入するようにしており、働く機会を増やすよう努めています。
70歳まで厚生年金の加入ができるため、納税額を増やすことで受給額を増やすことにもつながります。
短時間や数日でもいいので、働く機会を設けて、年金以外の収入を作りましょう。
健康寿命を延ばすために規則正しい生活を送る
健康寿命とは、健康的に生活できる期間のことです。
心身が自立し日常生活が制限されることなく生活できる期間を指しているため、平均寿命とは意味が異なります。
厚生労働省の2019年調査によると、男女の平均寿命と健康寿命は以下のとおりでした。
| 平均寿命 | 健康寿命 | |
| 男性 | 81.41歳 | 72.68歳 |
| 女性 | 87.45歳 | 75.38歳 |
男性は8.73年、女性は12.06年の差があります。
健康で過ごせる期間が長くなれば、医療費や介護費の費用負担が少なく、出費が抑えられる可能性が高まります。
バランスのよい食事やストレスを溜めこまないことを意識したり、睡眠や軽い運動の時間を確保したりして、健康寿命を延ばせるよう日々意識しましょう。
自宅を売却する
自宅を売却して資産を手に入れる方法です。
持ち家がある人限定となるため、賃貸暮らしの方は売却できる資産がないか確認してみましょう。
お金に困り、自宅売却すると決めた場合でも、しっかりと売却時のデメリットを確認します。
例えば、賃貸住まいにしようとした場合でも、高齢者は賃貸物件が借りにくい可能性があったり、環境の変化に慣れない場合もあったりします。
毎月固定で家賃もかかるため、ローンの支払いが終わっていた場合は再度住宅費がかかることにも注意しなければいけません。
売却しても住み続けられるリースバックや、自宅を担保にお金を借り、死亡時に売却して返済するリバースモーゲージというしくみもあります。
売却以外の選択肢があることを知り、メリット・デメリットの理解や、収支の計算をおこなった上で慎重に検討しましょう。
他人と比べない
「お金がなく、みじめな生活だ」と感じている人は、他人と比較している傾向にあります。
よって、他人と比べずに自分自身の生活を充実させることに意識を向けることが大切です。
お金がかからない趣味や娯楽を見つけたり、仕事をはじめてみたりしましょう。
また、お金の使い方や感覚に相違を感じる人が近くにいる場合は、距離をおくようにします。
生活基準を収入に合わせても幸せだと感じることを見つけていくと、みじめに感じることは少なくなるでしょう。
現役世代は資産運用をおこない資産を増やす
老後までに時間がある人は、積極的に資産形成をおこないお金を増やすことをおすすめします。
つみたてNISAやiDeCoなどを利用して長期資産形成を検討します。
リスクが全くない安全性が高い銀行普通預金ではお金は増やせません。
資産を増やすためには、多少のリスクがあっても積極的に資産運用をおこないます。
最低保証がないことや、資産が目減りすることに大きな不安を感じる人は、少額からでもよいので資産を分散させ長期的に運用してみましょう。
資産運用はどうすればいいかわからない、何を選べばいいか決められない、そんな方はファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
自分にあった金融商品を見つけ、早いうちに始めることが重要です
まとめ

高齢化が進行しており、人生100年計画を立てる必要が出ています。
また、少子化の影響で今後の年金制度がどうなるか分からないため、老後に安心して暮らすには、少しでも貯金を残しておくことが重要と言えます。年代ごとの平均貯金を見るとある程度は計画的に貯金をしている人が多いと言えますが、貯金ゼロの割合を見ると意外と高い割合に。
貯金ゼロの人たちは、年金収入だけでは老後の生活費を補い切れません。
老後にやばいという状況に陥らないためにも、計画的に貯金するように心掛けましょう。
貧乏は決して恥ではないですが、不便です。
いくら持っているかいくら稼いでいるかが綺麗ごと無で人の優劣である考え方もあります。
理想高く・目標高くいきましょう!
最後に、ある法則論について持論を含めてお伝えします。
今負けていても、周りを全員追い抜く法則です。
それは「ランチェスター法則」
これは
「人の1.7倍やれば大体勝てる
人の2倍やれば圧勝できる
人の2.3倍やれば元の才能が
完全に劣っていても負けない」
相手が週に40時間を使っているならあなたは80時間をかければ勝てる。
そんなシンプルな法則です。
近道ばかりさがすな、一番の近道は時間の使い方にある。
環境を変える事、そしてそこで燃焼しろ。手術はあなただ。
U-star電材ガス設備事業グループ 代表



